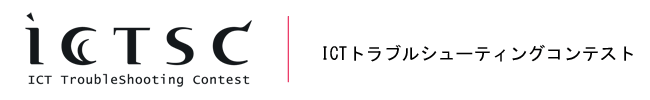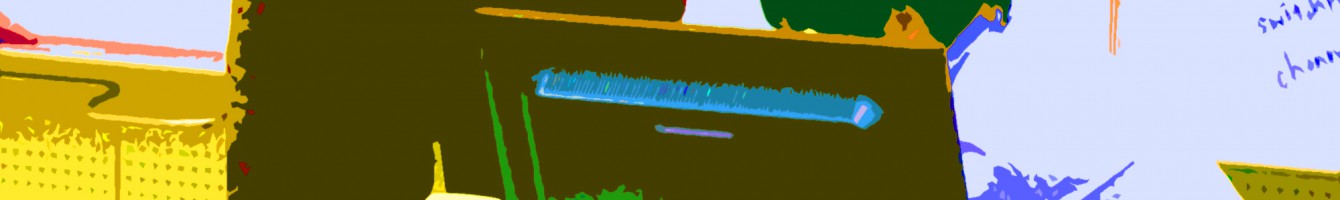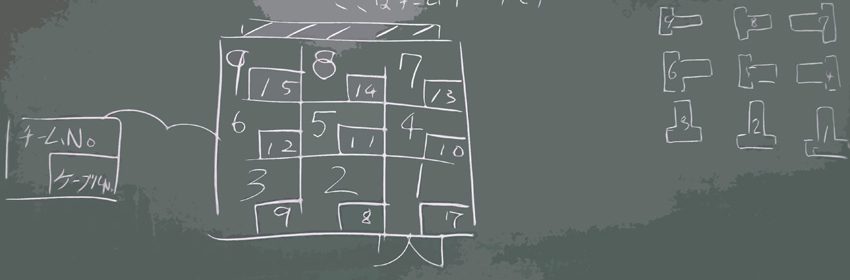スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポートまとめ

スカイアーチネットワークス杯 第8回ICTトラブルシューティングコンテストのレポートまとめです。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
準備期間~本番
スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポート 準備期間
スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポート DAY1
スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポート DAY2
告知~参加者募集期間
第8回ICTトラブルシューティングコンテスト実施要項/運営委員募集
スカイアーチネットワークス杯 第8回ICTトラブルシューティングコンテスト 参加チーム募集要項
スカイアーチネットワークス杯 第8回 ICTトラブルシューティングコンテスト 参加チーム決定
スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 「本選競技ルール概要」
運営、参加者、外部記事
運営
ICTSC8競技中に発生したトラブルの技術的な観点での解説
ICTSC8の問題解説 [ストーム制御とVSRX]
その他問題解説の記事はこちらに掲載予定。
参加者